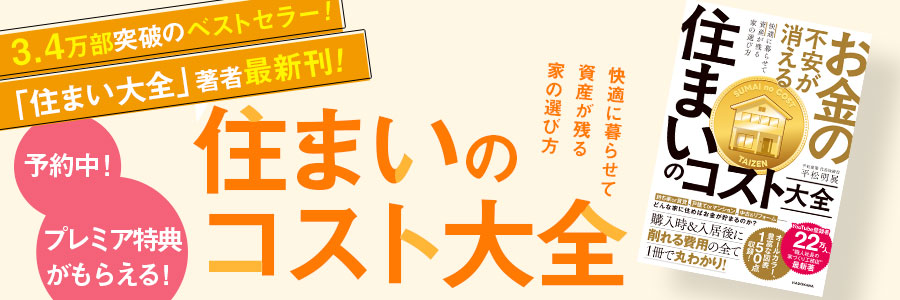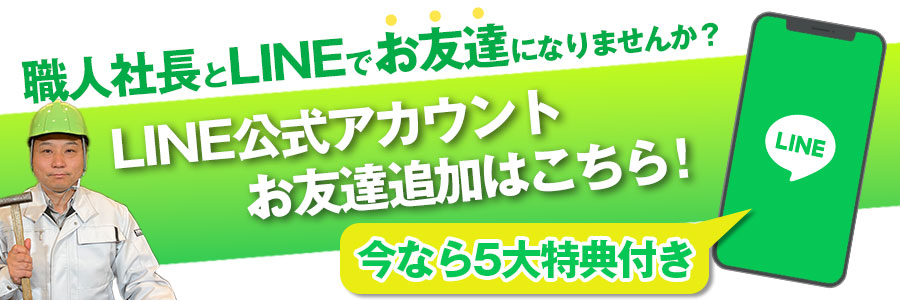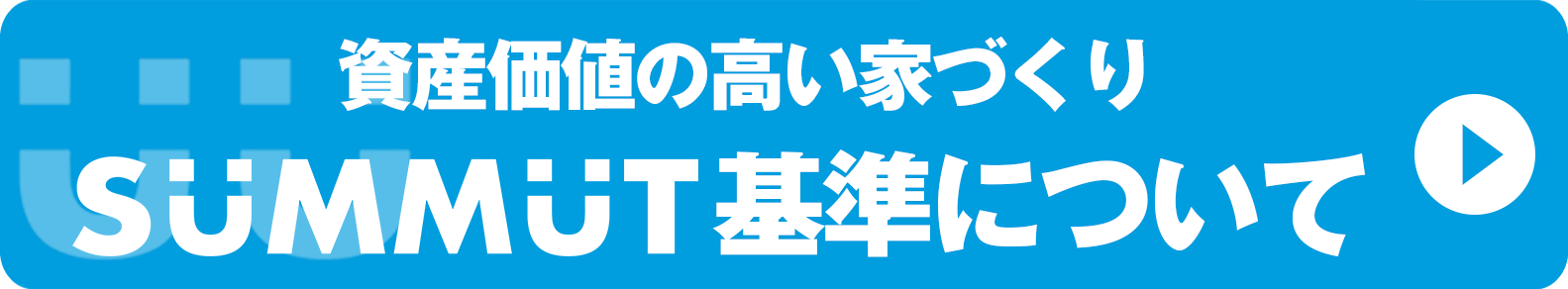家づくり用語集
あ行
あ
雨樋(あまとい)
屋根に落ちる雨水を集めて排水管に導く管状設備。金属製・樹脂製がある。適切な勾配と掃除口設置で詰まりや凍結・亀裂を防止する必要がある。
え
エコキュート(えこきゅーと)
空気中の熱と少量の電気でお湯を沸かす省エネ型の電気給湯器です。ヒートポンプ技術で夜間電力を利用し、高効率にお湯を貯めて給湯します。
エネファーム(えねふぁーむ)
家庭用燃料電池システム。都市ガスやLPガスから化学反応で発電し、その際に発生する高温の排熱を給湯や暖房に再利用することで、発電効率を高めつつCO₂排出を削減する。発電と同時に熱を利用する「コージェネレーション(熱電併給)」方式。
お
大壁パネル工法(おおかべぱねるこうほう)
柱や梁を下地材や仕上げ材で覆い隠す壁構造で、工場製作した耐力壁パネル(構造用合板に間柱・断熱材等を組み込んだもの)を現場で柱・梁に直接釘打ちして取り付ける軸組工法。柱が壁内に隠れるため洋風・モダンなデザインに適し、間柱の本数が少なく構成できるので材料コストを抑えやすい利点があります。一方で現場での釘打ち施工品質に職人技能の影響を受けやすい傾向があり、適切な施工管理が求められます。
か行
か
回遊動線(かいゆうどうせん)
家の中を行き止まりなく巡回する動線。家事効率化を狙う間取り手法で、家事負担軽減や採光・通風向上に寄与する。収納位置や家具配置と整合が必要。過度な回遊はコスト増につながる場合もある。
金物工法(かなものこうほう)
在来木造軸組工法で従来用いられてきた木材同士の仕口・継手(ほぞ穴・ほぞなど)を、高強度の金属プレートやボルトなどの接合金物に置き換えた工法です。木材を大きく削る必要がなくなるため柱や梁の断面欠損が減り、接合部強度が明確で安定した高耐力の構造躯体となります。プレカット加工と組み立て後のピン打ちで施工でき、熟練大工が減る中でも品質のばらつきを抑え工期を短縮できます。
壁倍率(かべばいりつ)
耐力壁の水平耐力の強さを示す指標。倍率が高いほど強固。一般的な合板よりも強度や耐久性が高い合板壁は3.3倍など。
換気設備(かんきせつび)
室内の空気を外気と入れ替える設備。給気口と排気口で構成され、自然換気に加え第一種(機械給排気)、第二種(機械給気)、第三種(機械排気)方式などがある。原則すべての建物で設置が義務付けられる。換気性能は熱交換器付き全熱交換機も含む。シックハウス対策にも必須。
外壁材(がいへきざい)
建物外周を覆い、建物の外観と防水・断熱・意匠性を担う材料。多彩な種類がある。外壁は断熱材の下地にもなる。メンテナンス性も重要。
ガス設備(がすせつび)
ガス管・給湯器・ガスコンロ等の設備。燃焼時の安全装置や排気ダクトも設置必須。ガス事業者の規定による設計・施工基準あり。
ガレージ(がれーじ)
自動車などを格納する車庫のこと。建物内部にビルトインするタイプもあり、住宅に併設する場合は構造・換気・安全性(ガス排気)に配慮が必要。スペース用途の一般呼称としても用いる。立体駐車場、ビルドインガレージとも区別。用途地域で面積制限など規制あり。
き
基礎工事(きそこうじ)
建物と地盤を結ぶ「基礎」を造る工事。コンクリートや杭で基礎を構築し、建物荷重を地盤に伝える。基礎形式(布基礎、べた基礎、杭基礎等)は地盤条件と建物規模で決まる。設計図通りの鉄筋配筋やコンクリート品質管理が重要。不同沈下防止策も検討。
気密測定(きみつそくてい)
住宅のすき間の量(気密性)を測定する試験。建物にファンを取り付け室内外の圧力差を利用し、C値(隙間相当面積)を算出する。気密性能が高いほど断熱・省エネ効果が向上する。主に新築木造住宅で実施。一般にC値1以下を良好とする。
給排水設備(きゅうはいすいせつび)
給水管・排水管・ポンプ等の設備全般。給水設備は外部の水源から水を取り入れ、排水設備は雨水・汚水を処理場へ排出する仕組み。住宅と公共設備をつなぐインフラ。浄化槽や雨水タンクなども関連設備。
金属系サイディング(きんぞくけいさいでぃんぐ)
ガルバリウム鋼板など金属板と断熱材を一体化した軽量外壁パネル。錆びにくく凍害にも強いが、熱伸縮や凹み傷に留意。重ね張りリフォームにも適す。
く
杭基礎(くいきそ)
地盤下深く鉄筋コンクリート・鋼管などの杭を打ち込んで支持層に到達させ、建物荷重を直接支持層に伝える基礎工法。支持層が深い場合や大規模建築で用いる。
空調設備(くうちょうせつび)
建物の温度・湿度・空気清浄度・気流を調整する設備。冷暖房・除湿・換気・加湿・空気清浄などの機能を包括し、エアコン、冷暖房機器、換気装置などで構成される。「空気調和設備」の略。全館空調システム(熱交換器等)も含まれる。
グラスウール断熱材(ぐらすうーるだんねつざい)
数μmのガラス繊維を絡めたマット状またはボード状の断熱材。繊維間に閉じ込めた空気が熱を伝えにくくし、λ値約0.038–0.050W/mK程度の性能を持つ。安価で施工性が高いが、湿気を吸うと断熱性能が低下するため防湿シートと組み合わせて使用する必要がある。
け
結露対策(けつろたいさく)
壁内結露・窓周り結露を防ぐため、十分な断熱・気密化、防湿シート設置、通気層確保、24時間換気などを計画的に組み合わせる設計・施工手法。断熱欠損や施工ミスによる局所結露に注意。
建築確認(けんちくかくにん)
建築主が新築・増改築前に、建築計画が建築基準法等の規定に適合しているか行政(建築主事)または指定確認検査機関に審査を受け、確認済証を得る手続き。工事着手前に必須。確認申請には設計図書の提出が必要。確認済後に工事着手、完了検査へ。
建築金物(けんちくかなもの)
建築物で使われる金属製付属部材の総称。接合金物や家具金具などが含まれる。接合金物は構造金物に含む場合もある。
建築基準法(けんちくきじゅんほう)
建築物の安全性・衛生面・構造・用途等の最低基準を定めた日本の法律。敷地面積・高さ・構造耐力・換気・採光・避難経路などの規定があり、新築・改築には基準適合が義務付けられる。これに違反した建物は是正指導や用途制限が課される。用途地域制限もこの法に規定。
建蔽率(けんぺいりつ)
敷地面積に対する建築面積(外壁の外側投影面積)の割合。例えば50%の敷地に建蔽率50%なら建築面積50㎡まで建築できる。用途地域により上限が規定され、敷地の利用効率を決める重要指標。
こ
硬質ウレタンフォーム(こうしつうれたんふぉーむ)
ポリウレタン樹脂を発泡させたプラスチック系断熱材。λ値約0.024–0.028W/mKの高断熱を薄い厚みで実現し、現場吹付けか板状ボードで使用。気密層を兼ねるため気密化しやすいが、可燃性のため石膏ボード等で防火被覆が必要。紫外線に弱く露出部は塗覆装など保護措置が求められる。
小屋裏(こやうら)
屋根下地と天井材の間にできる空間。断熱材や換気ダクト、点検通路として利用。通気を確保しないと結露・過熱の原因となるため、小屋裏換気が重要。
混構造(こんこうぞう)
木造・鉄骨造・RC造など異なる構造形式を組み合わせ、一棟の中で各部位に最適な構造を用いる工法。例えば、耐震性を重視する部分はRC造、コストや軽量性を重視する部分は木造で構成し、全体の性能バランスを最適化する。
剛床(ごうしょう)
外力にほぼ変形せず水平力を支持する高剛性な床構造。構造用合板床などで実現。
さ行
さ
サッシ(さっし)
窓枠に用いる枠材。外部開口部の断熱性・気密性・防音性に大きく関わる部材である。アルミサッシ、樹脂サッシ、木製サッシなどがある。ガラスの種類と組み合わせる。
在来工法(ざいらいこうほう)
木造軸組工法とも呼ばれ、伝統的に普及する木造工法。柱・梁・筋交いなどで骨組みを作り、外壁・屋根で囲む方法。地震や風に柔軟に対応できる。枠組壁工法(2×4)と対照。
し
仕上げ材(しあげざい)
内外装の最終仕上げに用いる材料の総称。室内壁クロス、床フローリング、外壁サイディングやタイルなど、建物の表面を覆って見た目や耐久性を決める材料。
斜線制限(しゃせんせいげん)
日照・採光・通風確保のため建物の高さを制限する規定。道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限などがあり、建物が境界線から架空の斜め線(斜線)を超えないように設計する。特に隣地斜線制限は隣地側の日当たりを守る規制。用途地域ごとに適用される斜線制限が異なる。
集合住宅(しゅうごうじゅうたく)
一つの建物内に複数世帯が居住する住宅形態。マンション・アパートなどが含まれる。一戸建て住宅の対義語で、共同住宅ともいう。規模により用途(1・2F店舗+上階住戸など)や避難計画が異なる。管理規約や共用部維持管理が特徴。
竣工(しゅんこう)
建築工事が完了し、設計図通りに出来上がった状態。竣工後に完了検査(中間検査を含む)を経て確認済証が交付され、建物使用開始の手続きが行われる。竣工式は完成を祝う式典。竣工後は保証・アフターサービスが始まる。
照明設備(しょうめいせつび)
建物内外を照らす電気設備。蛍光灯やLEDなどの照明器具から配線・スイッチまでを含み、室内・外観を明るくする。デザイン性と省エネが重視され、高効率ランプや調光システムも多用される。LED化や調光・調色のニーズ増加。
真壁パネル工法(しんかべぱねるこうほう)
木造軸組において柱や梁を室内に現しにする壁構造で、柱と柱の間に予め工場製作された壁パネル(構造用面材+間柱+断熱材など一体化パネル)をはめ込んで施工する工法。柱間に耐力壁パネルを収めるため伝統的な和風建築に多く見られる納まりで、工場生産のパネルを現場で差し込むだけで取り付けられるため少人数でも効率よく施工できます。柱が見える真壁ならではの意匠性を保ちながら、耐震性の高い面材壁を取り入れられる点が特徴です。
地鎮祭(じちんさい)
建築着工前に神職を招き、土地の守り神に工事の安全と建物の繁栄を祈願する伝統的儀式。玉串奉奠や鍬入れの儀などを行う。
地盤改良(じばんかいりょう)
軟弱地盤や埋戻し地盤を杭状改良・薬液注入・土壌置換などで強化し、建物荷重を安定して支えるよう改善する施工。改良方式は地盤調査結果とコスト・施工性で選択する。
地盤調査(じばんちょうさ)
建物着工前に土地の支持力(地耐力)や軟弱地盤の有無などを明らかにする試験。ボーリングやSWS試験、平板載荷試験などの方法で、建物が地盤に沈下しないかを確認する。結果に応じて地盤改良が必要か判断する。宅地造成時にも実施。
住宅性能表示制度(じゅうたくせいのうひょうじせいど)
「品確法」に基づき、耐震・断熱・維持管理など10分野の性能を等級で評価し第三者評価機関が証明書を発行。性能を可視化することで比較検討が容易になり、住宅取得後のトラブル軽減や融資・保険・補助金の要件にも活用される。
住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
住宅取得の借入金残高に応じて所得税・住民税を減額できる税制優遇措置。居住開始後10年間が一般的で、年末残高の1%を上限に控除。一定の性能(省エネ等)要件を満たす場合は控除期間延長も可能。
樹脂系サイディング(じゅしけいさいでぃんぐ)
塩化ビニル製の中空ボード状外壁材で、腐食・塩害に強く基本的に塗り替え不要。軽量で施工性が良いが、熱変形や海外製品の品質差に注意。
上棟(じょうとう)
建物の主要構造が組みあがり、屋根の最上部に棟木を取り付ける工程。工事着工から完成の中間に位置し、上棟式を行い工事の安全を祈願する習慣がある。「棟上げ」「建前」とも呼ぶ。
す
水平構面(すいへいこうめん)
床や屋根など水平の面のこと。水平荷重を分散し安定性を高める。剛床化(床面を剛にする)は水平構面強度を高める工法。
スキップフロア(すきっぷふろあ)
1つの階層内に複数の段差を設けた間取り。階段で一段上げ下げすることで中2階空間を作り、空間の広がりや変化を演出する設計手法。段差により部屋を緩やかに仕切る効果もある。建築費や階高に配慮が必要。全館空調設置時の気流計画が重要になる。
隅切り(すみきり)
敷地の角を斜めに切り取り、道路斜線制限や見通し確保、セットバック要件をクリアする処理。接道幅員の確保や安全性向上に寄与する。
せ
制震構造(せいしんこうぞう)
建物に制震装置(ダンパー等)を組み込み、地震の揺れを吸収・分散させる構造技術。建物の変形や損傷を抑える効果があります。
制振ダンパー(せいしんだんぱー)
地震時に建物の揺れエネルギーを吸収・減衰させる装置。柱・梁の接合部や壁内部に設置し、オイルダンパーや摩擦ダンパー、粘弾性ダンパーなどで構成される。建物の応答加速度を抑え、変形や損傷を軽減する。制震構造の中核部材として、耐震性能の向上に寄与する。
セルロースファイバー断熱材(せるろーすふぁいばーだんねつざい)
新聞古紙などを繊維化しホウ酸などで防燃・防虫処理した断熱材。専用機械で壁内に隙間なく吹込むため調湿性・吸音性に優れ、λ値約0.034–0.041W/mK。自己消火性を示し難燃3級相当。施工費用はやや高めで、吹き込み密度のムラに注意。
ち
蓄電池(ちくでんち)
充放電を繰り返し利用できる二次電池。太陽光発電や夜間電力などで充電し、必要時に放電して住宅負荷を賄う。停電時のバックアップやピークシフトにも使われ、省エネ・災害対策に有効。リチウムイオン電池が主流。容量と出力に応じた蓄電池ユニットが各社から供給される。
た行
た
太陽光発電(たいようこうはつでん)
太陽光の光エネルギーを太陽電池モジュールで直接電気に変換する発電システム。住宅屋根やカーポートに太陽電池パネルを設置し、発電した電力を自家消費し余剰は売電する。英語でPV(Photovoltaic)発電。系統連系や蓄電池との組合せでZEHに寄与する。
耐力壁(たいりょくへき)
地震や風圧など水平荷重に対抗する壁。柱と梁の骨組みに斜め材や構造合板を貼って補強し、地震力を建物下部へ伝える。筋交い壁やパネル壁が該当。
建具(たてぐ)
ドア・窓・ふすま等、開口部に設ける可動式の仕切りの総称です。開閉して部屋を仕切ったり出入りしたりする要素で、デザインや材質によって室内の雰囲気や断熱・気密性能にも影響します。
第一種換気方式(だいいっしゅかんきほうしき)
給気(外気を室内へ)と排気(室内空気を外へ)の両方を電動ファンで強制的に行う方式。熱交換器で排気の熱・湿度を回収でき、高気密高断熱住宅でも安定した換気性能と省エネ効果を両立できる。機器・ダクト工事費やメンテナンス負担が大きい。
第三種換気方式(だいさんしゅかんきほうしき)
排気だけを電動ファンで強制的に行い、給気は給気口や隙間から自然に流入させる方式。初期・維持コストが低くシンプルだが、給気量が気圧差や気密性に左右されやすく、冷暖房負荷が増えやすいのが欠点。
第二種換気方式(だいにしゅかんきほうしき)
給気だけを電動ファンで強制的に行い、排気は建物の正圧で自然に行う方式。室内を正圧に保つことで花粉や塵埃の侵入を抑えやすいが、排気量が不安定でキッチンや浴室など局所排気が別途必要なため、一般住宅での採用例は少ない。
断熱材(だんねつざい)
建物の内外の温度差による熱の移動を抑える材料。グラスウールや硬質ウレタンなど種類が多い。壁・天井・床に使用し、快適性と省エネに寄与する。熱絶縁材ともいう。用途や耐火性能で種類が分かれる。
断熱等性能等級(だんねつとうせいのうとうきゅう)
住宅性能表示制度の断熱・省エネ評価等級。外皮の熱性能や窓の日射取得などに基づき1~7等級にランク付けし、高い等級ほど高断熱・省エネ仕様である。長期優良住宅認定の断熱基準も含む。等級4が現行の省エネ基準相当(平成25年基準)で、等級5~7はさらに高い次世代断熱水準として新設されました。
ち
着工(ちゃっこう)
確認済証交付後、実際に工事を開始する段階。仮設工事・根切り・基礎工事など目に見える工事に着手することを指す。「起工」とも呼ばれる。
中間検査(ちゅうかんけんさ)
工事中に構造躯体など重要部分を現場で検査し、建築基準法適合を確認するもの。基礎・柱・梁・耐力壁などの施工状況を審査し合格すると中間検査合格証が交付され、次工程に進める。検査不要な小規模住宅もある。確認済み住宅は検査が義務付けられる。
長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)
長期にわたり良好に住み続けられる住宅を普及させる制度。耐震性・断熱性・維持管理計画等の厳しい基準を満たし、認定を受けた住宅には税優遇・融資優遇がある。
つ
通気層(つうきそう)
外壁裏や屋根下地と仕上げ材の間に設ける数cmの空間。壁内結露を防ぎ、夏季は日射熱を排出して遮熱効果を発揮。下端・上端に通気口を設け、自然対流で湿気や熱気を逃がす。
て
低炭素住宅(ていたんそじゅうたく)
CO₂排出量の少ない住宅を促進する制度。高断熱・省エネ設備・再エネ導入等で所定の低炭素基準を満たすと自治体の認定を受けられ、固定資産税減免等の優遇措置がある。長期優良住宅と併用できるケースも多い。
鉄筋コンクリート造(てっきんこんくりーとぞう)
鉄筋を組んだ型枠にコンクリートを流し込んで柱・梁を作る構造です。鉄筋の引張強度とコンクリートの圧縮強度を併せ持ち、耐震性・耐火性・防音性に優れます。RC造と同義。
鉄骨造(てっこつぞう)
家の柱や梁など骨組みに鉄鋼(鋼材)を用いた構造です。鋼材の強度により耐震性・耐久性が高く、柱が細いため大開口部の設計も可能です。S造と同義。
店舗併用住宅(てんぽへいようじゅうたく)
一棟に店舗・事務所等の商業スペースと居住スペースが併設された住宅。1Fに店舗、2F以上を住居とする例が多い。居住と商業の用途混在のため防災や建築制限にも留意が必要。都市部の住宅事情で多い形態。間取り設計や階高設定に工夫が必要。
電気設備(でんきせつび)
配電盤・コンセント・配線等の電力供給設備。照明・コンセント・家電に電気を供給し、安全な運用を確保する。受電・変電設備も含む。電力会社からの受電点から建物内へ分配する。スマートメーターやBEMSも普及。
と
動線(どうせん)
人の移動経路を示す設計概念。生活や家事の動きやすさを考え、廊下や階段位置を計画する際に用いる考え方。家事動線・生活動線・来客動線など用途別にプランすることで快適性が向上する。図面上で線で示すことも多い。導線とも書く。
土台(どだい)
木造で基礎コンクリート上に敷かれる水平の木材。柱からの荷重を基礎に伝える。ヒノキ・ヒバなど耐久性の高い木材を用いる。
な行
な
内装材(ないそうざい)
床・壁・天井の内部仕上げ材や下地材の総称。木質系、布・紙系、石材系、塗装など多種多様。
ぬ
布基礎(ぬのきそ)
建物周囲に帯状の鉄筋コンクリートを打設する基礎工法。地耐力が十分な場合に採用しやすくコストを抑えられるが、ベタ基礎に比べ湿気・シロアリ対策は別途必要。
の
軒天(のきてん)
軒裏の天井仕上げ部分。透気孔を設けることで小屋裏通気を確保し、夏の温度上昇や結露を防止する役割も持つ。
軒の出(のきので)
屋根の軒先が外壁から前方に張り出す長さ。雨水が壁面にかかるのを防ぎ、夏の日射遮蔽や意匠性向上にも効果的。長さは構造や積雪深、日射条件を考慮して設計される。
は行
は
柱(はしら)
建物の床や屋根を支える縦架材で、鉛直荷重を基礎に伝える構造部材。柱脚には基礎金物を使用。
梁(はり)
建物内部の柱などにかかる荷重を横方向に支える横架材。柱の上に架けて、上部からの荷重や水平荷重を受けて次の柱に伝える構造部材。建築用語では横架材の意。
ふ
吹き抜け(ふきぬけ)
複数階の空間をつなげ、階をまたぐ高さをもたせた開放部。1階の天井を作らず2階以上まで空間が続くため、室内に開放感と採光・通風効果を生む。リビング吹き抜けなどに用いる。断熱・空調コストは上階へ影響する。安全柵や落下防止に注意。
複層ガラス(ふくそうがらす)
2枚以上のガラスを間隔層(アルゴンガス等封入)で構成し、断熱・遮音性能を高めた窓ガラス。室内外の温度差による結露抑制効果も高い。
フラット35(ふらっとさんじゅうご)
民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する長期固定金利型の住宅ローン商品です。最長35年の全期間固定金利で返済計画が立てやすいのが特徴です。
フラット35S(ふらっとさんじゅうごえす)
長期固定金利住宅ローン「フラット35」の優遇版。耐震性、省エネ性など一定の性能条件を満たす住宅取得者は、当初5~10年間の借入金利が低減される制度。国交省所管。ZEHや高断熱住宅取得時に金利優遇。住宅ローン控除とは別の優遇策。
へ
ベタ基礎(べたきそ)
建物の底版を全面に鉄筋コンクリートで打設する基礎工法。底面全体で荷重を分散し地盤沈下を抑制、湿気やシロアリ侵入も防ぎやすい。
別荘(べっそう)
主に休暇利用を目的として建てられた住居。拠点住宅とは異なり、居住スペースよりレジャー・リゾート的要素が重視される。高断熱や空調設備を簡略化する場合も多い。別荘地の景観規制や防災(山林火災など)対策が重要。自家用別荘・借別荘がある。
ほ
防蟻処理(ぼうぎしょり)
土台・柱脚など木部や基礎周辺に薬剤を塗布・散布し、シロアリ侵入を防ぐ施工。一般薬剤は効果約5年で、薬剤再処理や樹種選定(耐蟻性木材)を組み合わせる場合が多い。
防湿シート(ぼうしつしーと)
ポリエチレン膜などで作る湿気遮断膜。壁内結露防止のため、室内側(気温高く湿度高い側)に張り、壁内への水蒸気侵入を抑制する。シート継ぎ目の気密処理が性能維持の要。
ま行
め
免震構造(めんしんこうぞう)
建物の基礎と地盤の間に免震装置を設置し、地震の揺れを直接建物に伝えない構造技術。基礎部分で揺れを受け流し、建物への衝撃を大幅に減らします。
も
木質系サイディング(もくしつけいさいでぃんぐ)
杉・ヒノキなど天然木/集成材の外壁材。自然な風合いと意匠性が魅力だが定期的な再塗装・防腐処理が必要。木材の反り・割れ防止の下地通気とメンテ計画が重要。
や行
や
屋根材(やねざい)
屋根を保護する仕上げ材料。瓦、金属板、シングル材など。屋根下地を保護し、防水・断熱・耐風性を確保する。葺き替えメンテナンスで耐久性向上可能。
ゆ
床暖房(ゆかだんぼう)
床下に温水パイプや電熱線を配置し、足元から部屋を暖める暖房設備です。ふく射熱により室内全体がムラなく暖まり、快適な暖房効果があります。
ユーティリティ(ゆーてぃりてぃ)
住宅では洗濯や家事作業用の専用スペースを指すことが多い。家事動線上に配置し、洗濯機・物干し・収納などをまとめて置くことで効率を高める。水回り家電置場やサービスヤードと重なる概念。最近はマルチユースの家事室やパントリーを含めて「ユーティリティ」と呼ぶことも多い。
よ
窯業系サイディング(ようぎょうけいさいでぃんぐ)
セメント質原料に木質繊維などを混合し板状に成形した外壁材。防火性・耐久性が高く、色柄・意匠バリエーションが豊富。10~15年ごとの再塗装・シーリング打替えが必要。
容積率(ようせきりつ)
敷地面積に対する延べ床面積の割合を百分率で表した指標。例えば容積率200%なら、100㎡の敷地に最大200㎡の延床が建築可能。都市計画で上限が定められ、建物の規模制限に使われる。敷地が大きいほど建てられる床面積が増え、容積率制限は地区によって異なる。
ら行
ら
ラーメン構造(らーめんこうぞう)
柱と梁を剛接合(モーメント接合)し、一体の骨組として水平・鉛直荷重を受け止める構造方式。フレーム全体で力を分散するため、耐震・耐風性能が高く開口部や大スパン空間の確保が容易。鉄骨造・RC造で多用される。SE構法など木造ラーメン工法も登場。
ろ
ロックウール断熱材(ろっくうーるだんねつざい)
玄武岩やコークスなどを高温で溶融→繊維化し、マット・ボード状に成形した無機系断熱材。耐火性・耐熱性に優れ、吸音性能も高い。吸湿・水濡れにも強く、λ値約0.036–0.045W/mKと安定した断熱性能を示すが、グラスウールより価格・重量が大きくなる。施工時の粉塵対策や取り扱い注意が必要。
ロフト(ろふと)
屋根勾配内や天井高の余裕部分を活用した中二階的な収納または居室スペース。固定階として扱われる場合は建築基準法上の床面積に含まれるため、高さや面積規定に注意が必要。
A~Z
ICT(あいしーてぃー)
建築では建設IT化全般を指す。現場でのクラウド共有、ドローン測量、AI設計支援、IoT設備監視など、情報通信技術を活用して設計・施工・維持管理の効率化・高品質化を図る概念。建設DXとも呼ばれる。BIM/CIMや地理情報システム(GIS)とも連携。
SE構法(えすいーこうほう)
強度安定した集成材(幅120×120~360×120 mm)と専用金物(Sボルト)を用い、柱と梁をラーメン構造(剛接合フレーム)で緊結する木造工法。詳細な構造計算(鉄骨・RC並)を一棟ごとに実施し、施工は専用工場でボルト締め付けを行うことで高い精度を担保。大スパンかつ壁の少ない自由な間取り設計を可能にし、耐震等級3相当の耐震強度を実現する。
LCCM(えるしーしーえむ)
ライフサイクルカーボンマイナス住宅。建設・運用・廃棄までのライフサイクルで排出されるCO₂総量をマイナスとする住宅で、断熱高性能+創エネでCO₂収支をマイナス化することを目指す。政府が推進する新性能基準。ZEH+廃棄時排出ゼロを目標とする。
CASBEE(きゃすびー)
建築物総合環境性能評価システム(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency)の略。建物の環境負荷(エネルギー・資材・環境対策)と室内環境質を総合評価し、格付けする制度。国交省監修。ラベル(S~C評価)で建築物の環境品質を示す。
CAD(きゃど)
コンピュータを用いて建築図面や設計図面を作成・編集する技術。2Dと3Dの両方があり、図面の作図効率化と修正性向上を目的とする。BIMソフトの基礎技術でもあり、現場でのCNC加工指示データにも利用される。従来の手書き図面に比べ高速・高精度。DWG/DXFなどのファイル形式。
Q値(きゅーち)
(旧)住宅の断熱性能を示す熱損失係数。住宅全体の熱が逃げやすさを示し、Q値が小さいほど断熱性が高い。温度差1℃で1時間に逃げる熱量(W)を床面積(㎡)で除した値で計算される。近年は換気熱損失を含む計算などからUa値に移行している。
C値(しーち)
住宅の気密性を表す数値で、相当隙間面積ともいう。住宅全体の隙間面積(cm²)を延べ床面積(㎡)で除した値で、数値が小さいほど気密性が高い。高気密住宅では1.0cm²/m²以下を目指す。気密測定で確認。
SW工法(すーぱーうぉーるこうほう)
LIXIL社が開発した高性能木造住宅工法。在来木造軸組と2×4工法の長所を組み合わせ、硬質ウレタンフォーム充填の高断熱パネル「スーパーウォール」で天井・壁・床を箱型に一体化することで、住宅全体を魔法瓶のような高気密・高断熱のモノコック構造にします。全棟で気密測定を実施しC値1.0以下を確保、高断熱サッシと計画換気システムも採用して一年中快適な室内環境と優れた省エネ性を実現。壁倍率4.3倍のパネルで地震力を面で分散し、木造最高水準の耐震性と耐久性(壁内結露30年以上無発生保証)を誇る工法です。
高性能な断熱・耐震パネルによるパッケージ工法で、施工には認定工務店が必要。在来工法に比べ初期コストは高いですが、快適性と省エネルギー性能でメリットがあります。
ZEH(ぜっち)
ゼロ・エネルギー・ハウス(Zero Energy House)の略。省エネ基準を超える高断熱・高効率設備+太陽光発電等で、一次エネルギー収支を正味ゼロにする住宅。補助金制度あり。
WB工法(だぶるぶれすとこうほう)
夏季は壁内通気で湿気と熱気を逃がし、冬季は形状記憶合金の自動開閉通気口で壁内を密閉して断熱層とする、「呼吸する家」を実現した独自の木造工法です。従来の高気密住宅とは異なり、壁体内に通気層を設けて化学物質や湿気を透過・排出する仕組みにより、機械換気に頼らず結露しにくい快適な室内環境を目指します。日本の高温多湿な気候に着目し、夏は通気で涼しく冬は断熱で暖かい相反する性能を両立させた工法です。
「WB」は*ダブルブレス(Double Breath)*の略称で、WB工法の施工には専用部材・加盟工務店が必要です。
BIM(びむ)
3次元の建築モデルにコスト・部材・設備・維持管理情報など属性データを付加し、設計~施工~維持管理全工程で情報共有・活用する手法。設計・施工の効率化と品質向上を実現するワークフローで、現在主流の技術。CADとの違いは情報統合の広さ。CDE(共通データ環境)などICT支援技術と併用する。
V2H(ぶいつーえいち)
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)のバッテリーに蓄えた電力を家庭に供給し、非常時のバックアップ電源や電力ピークシフトに活用するシステム。双方向充放電機能と専用のパワーコンディショナが必要。災害時の自立運転にも利用可。Vehicle to Home の略。
HEMS(へむす)
Home Energy Management System(ホームエネルギー管理システム)の略。家中の電気やガスの使用状況を見える化し、家電や照明を自動制御して省エネ最適化を図るしくみです。
BELS(べるす)
建築物エネルギー性能表示制度。建物のエネルギー消費性能・断熱性能等を第三者評価機関が評価し、星や家マーク等で分かりやすく表示する省エネ性能評価制度。住宅からオフィス・商業施設まで幅広い用途で利用可能。省エネ性能の見える化ツール。
Ua値(ゆーえーち)
外皮(窓・壁・床・屋根)全体の熱貫流率の平均値。建物内外の温度差1℃あたりに外へ逃げる熱量(W)を外皮面積(㎡)で除した数値。値が小さいほど断熱性が高い。省エネ基準では地域別にUa目標値が定められている。